無理もないよ。
三菱商事 洋上風力発電計画 撤退の方向で最終調整
2025年8月26日 19時50分
秋田県と千葉県の沖合で計画されている洋上風力発電について、事業を中心的に進めてきた大手商社の三菱商事が、コストの大幅な増加などを理由に撤退する方向で最終調整を進めていることがわかりました。洋上風力発電を取り巻く環境は厳しさを増しており、国のエネルギー政策への影響も避けられない見通しです。
NHKニュースより
日本政府は、「洋上風力をエネルギー安全保障の切り札」と持ち上げてきたけど、現実は中国製に依存するしかなく、三菱商事まで撤退を決めた。これで安全保障って言うんだから、冗談にしか聞こえない。
- 秋田県と千葉県の沖合で計画されている洋上風力発電計画で、三菱商事が撤退
- 再生エネルギー発電推進の方針を見直せ
- 三菱商事の入札は見積もりが甘かったが、他の事業者だったら撤退しなかったかというと、そういうことではない
「自然に優しい」再生エネルギー発電
世界を牛耳る支那メーカー
NHKは、この報道について「国のエネルギー政策への影響も避けられない見通し」などといっているが、今や世界は脱炭素社会志向から冷めつつある。というか、もともと「脱炭素」は掛け声だけだった国家も結構多いんだよね。
特に風力発電の質はお世辞にも高いとは言えない。
ドイツの洋上風力発電事業、中国製タービン取りやめ国内製に
2025年8月26日午後 12:57
ドイツの北海の洋上風力発電事業で、中国企業へのタービン発注が取り消され、国内企業に切り替わる見通しとなった。
ウォーターカント(Waterkant)計画は、2028年末までに送電網に接続する予定で約40万世帯分の電力供給を見込んでいる。
ロイターより
もともと「再生可能エネルギー発電」に着眼したのは、他から資源を輸入せずに発電可能であるという優れた点があるからだった。でも、同時に天候任せの発電手法は電力の安定供給に欠けるので、「環境にイイヨね」という点をアピールして増やしていった。
ところが、実は太陽光も風力も中国製頼みが当たり前。
今や、世界の風車メーカーのトップ10のうち6社が支那メーカーで、しかも上位4社を独占している。

ゴールドウィンド(金風科技)、Envision(遠景能源)、Windey(遠達)、Mingyang(明陽智慧能源集団)で5割を占めている。
そうすると、新規建造にもメンテナンスにも支那に頼らざるを得なくなってしまう。
ドイツの危機感
だから、ドイツが支那製を避るのであれば、自ずと国産化しか選択肢がない。
欧州連合(EU)欧州委員会は昨年、加盟5カ国が中国製の風力タービンメーカーによって市場競争が損なわれている可能性について調査を開始した。明陽智能能源への発注が発表されたのは、その後で、欧州のタービン業界から批判の声が上がり、ドイツ政府も懸念を持った。
ロイター「ドイツの洋上風力発電事業」より
別に「支那製=悪」という気はないのだが、ここまで支那製のタービンが幅をきかせている理由を考えると、ドイツの懸念も分かるのである。自国の安全保障に関わる話だからね。
ところが日本はどうだろう。太陽光も風力も中国製頼みで、自国産業は衰退。安全保障を叫びながら、エネルギー政策は“依存の輸入保障”と化している。
いつものパターン
どうしてこうなってしまったのか?
中国の風力発電タービンメーカーの競争激化、収益は低下
2024年02月28日
米国調査会社ブルームバーグNEFは2月19日、2023年の中国における新規風力発電設置容量が前年比58%増の77.1ギガワット(GW)となり、過去最高の見込みと発表した。
~~略~~
中国における風力タービンメーカーの競争が激しくなり、風力タービンの価格が低下し、関連企業の収益は低下している。過去2年間において、外資メーカーが中国市場において風力発電設備を設置したのは、デンマークの大手風力発電メーカーのべスタスのみとなった(「BNNブルームバーグ」2月19日)。
JETROより
支那国内で五カ年計画に「風力発電の導入」が明記され、支那政府の政策的保護や補助金投入などの後押しもあって一気に製造環境が整えられ、量産体制と販売網を構築。
そして、巨大なタービンを効率よく安価に製造可能になったことで、支那製タービンが世界を席巻する流れになったわけだ。
支那国内で矛盾が広がる
ここでちょっと面白い話がある。
支那国内で太陽光発電と風力発電を頑張った結果、火力発電を増やさざるを得なくなってきたという事実だ。
中国で「太陽光・風力」発電所の建設ラッシュ続く
2025/02/17 16:00
中国で再生可能エネルギー発電所の建設ラッシュが続いている。(エネルギー政策を所管する)国家能源局が1月21日に発表したデータによれば、中国国内で2024年に新設された太陽光発電装置の設備容量は前年比28%増の2億7700万kW(キロワット)、風力発電装置は同4.5%増の7934万kWに上り、そろって過去最高を記録した。
火力、水力、原子力なども含めた2024年の総新設容量は4億2900万kWであり、太陽光と風力だけで全体の83%を占めたことになる。
東洋経済より
前述したように、太陽光発電も風力発電も安定した発電は出来ない。投げっぱなしの太陽任せ、風任せの発電方法で、依存すれば依存するほどバックアップ発電方法が必要となる。
再エネ発電の急増により中国全体の発電能力は電力需要を上回るが、地方や時間帯による需給のミスマッチはむしろ拡大している。そのため、広東省や江蘇省などの電力の大消費地では、火力発電所の増設が続いているのが実態だ。
東洋経済「中国で「太陽光・風力」発電所の建設ラッシュ続く」より

そして、この光景を見ると「環境に優しいとは一体どんな意味なの?」と考えてしまう。
さておき、もう支那国内で再生エネルギー発電を広げるのが難しくなり、あまりに安価生産を続け過ぎて外国に積極的に安売りされる展開になったのだ。
損切り出来るか
というわけで、冒頭に紹介したように、三菱商事は逃げ出すことを決めたようだ。
え?何が「というわけ」だって?
三菱商、秋田・千葉県沖の洋上風力発電開発を中止 中部電は170億円の損失見込む
2025年8月27日午後 3:05
三菱商事は27日、秋田県と千葉県沖の計3海域で計画していた洋上風力発電事業について、開発を取りやめると発表した。当初の想定を上回る事業環境の変化を受け、事業性の再評価を行っていた。開発中止に関する損失は大部分を過年度に計上済みで、追加損失が生じる場合でも限定的になる見込みとしている。
ロイターより
いや、「支那のタービンを買って風力発電しても、利益出せないよね」って話になったということなんだな。
洋上風力発電にはメンテナンスで凄くお金がかかることも分かっているし、その割に得られる電力がショボく、これを陸上に運ぶのにまたお金がかかるんだよ。更に発電安定性を担保する為に、火力発電など補助発電手段を整備する必要がある。
事業性なんてあるわけがない。
エネルギー基本計画は風力発電について、陸上に比べて大規模開発が可能で、特に洋上風力は今後コスト低減が見込まれ「再生可能エネルギーの主力電源化に向けた『切り札』」と位置付けている。陸上より風速が速く、騒音や景観の問題も起きにくい長所があるとされる。
ロイター「三菱商、秋田・千葉県沖の洋上風力発電開発を中止」より
寝言書いているなぁ。
エネルギー安全保障とは??
そもそも、「エネルギー安全保障」とか言いながら基本計画を書いたみたいだけど。
蓋を開けてみれば、太陽光パネルも風車タービンも支那から買い付けて、化石燃料は中東から。で、シーレーンのチョークポイントを支那に狙われている状態なんだよね。
そのくせ、原子力発電の再稼働は遅々として進まない。
エネルギー安全保障とは……。え?ブラックジョーク?
追記
コメントを戴いた件について、少し検討してみたい。
安値受注の疑い
何についてかといえば、三菱商事が安値で受注したのでは?という件である。
「秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖」、「秋田県由利本荘市沖」、「千葉県銚子市沖」における洋上風力発電事業者の選定について
令和3年12月24日
経済産業省及び国土交通省は、再エネ海域利用法に基づく海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域である「秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖」、「秋田県由利本荘市沖」、「千葉県銚子市沖」における選定事業者について、それぞれ、「秋田能代・三種・男鹿オフショアウィンド」、「秋田由利本荘オフショアウィンド」、「千葉銚子オフショアウィンド」を選定しました。
経済産業省プレスリリースより
ここに出てくる「~オフショアウインド」という事業体全てに三菱商事が一枚噛んでいた。
(1)秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖の評価結果
| 事業者名 | 評価点合計(240点満点) | 価格点(120点満点) | 事業実現性に関する得点(120点満点) | 選定事業者 |
|---|---|---|---|---|
| 秋田能代・三種・男鹿オフショアウィンド | 208 | 120(13.26円/kWh) | 88 | ○ |
| 公募参加事業者1 | 160.52 | 87.52 | 73 | |
| 公募参加事業者2 | 157.77 | 93.77 | 64 | |
| 公募参加事業者3 | 149.35 | 71.35 | 78 | |
| 公募参加事業者4 | 127.04 | 59.04 | 68 |
(2)秋田県由利本荘市沖の評価結果
| 事業者名 | 評価点合計(240点満点) | 価格点(120点満点) | 事業実現性に関する得点(120点満点) | 選定事業者 |
|---|---|---|---|---|
| 秋田由利本荘オフショアウィンド | 202 | 120(11.99円/kWh) | 82 | ○ |
| 公募参加事業者5 | 156.65 | 83.65 | 73 | |
| 公募参加事業者6 | 149.73 | 58.73 | 91 | |
| 公募参加事業者7 | 144.20 | 78.20 | 66 | |
| 公募参加事業者8 | 140.58 | 62.58 | 78 |
(3)千葉県銚子市沖の評価結果
| 事業者名 | 評価点合計(240点満点) | 価格点(120点満点) | 事業実現性に関する得点(120点満点) | 選定事業者 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉銚子オフショアウィンド | 211 | 120(16.49円/kWh) | 91 | ○ |
| 公募参加事業者9 | 185.6 | 87.60 | 98 |
事業評価自体は何れも高得点だと判定されていて、価格点でほぼ満点をとっている。この価格点というのは、売電価格のことを言っているのだと思われ、事業収益を見越した価格設定にしてあるのだと理解すれば良い。FIT上限価格29円/kWhの1/2~1/3というのが、三菱商事が参加する事業者の提示額である。
したがって、安値入札だったというのはほぼ確実だと思われる。
撤退判断の妥当性
その上で、今回の撤退に繋がった。
国内洋上風力発電事業に係る事業性再評価の結果について
2025年8月27日
三菱商事株式会社(以下「当社」)は、当社子会社である三菱商事洋上風力株式会社を代表企業とするコンソーシアムを通じて、以下3海域(※)において各プロジェクト会社を設立し、発電事業者として洋上風力発電所の開発を進めてまいりました。
(※)3海域…秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖/秋田県由利本荘市沖/千葉県銚子市沖
本年2月に公表致しました通り、公募参画当初の想定を上回る事業環境の変化を受け、事業性の再評価を行いました結果、遺憾ながら3海域の開発を取り止めざるを得ないとの判断に至りました。
地元の方々をはじめ、関係する皆様のご期待に応えられない結果となったことを重く受け止めております。
三菱商事のサイトより
大幅な安値であった可能性が高く、「最初から無理な価格で入札したんじゃないの」と揶揄されても仕方がない側面はあろう。
ただし、アメリカが風力発電に見切りを付けた報道や、ドイツが風車タービンを国産化する報道、既に現状価格維持が不可能になっている支那企業(おそらく風力タービンの有力な調達先)の現状、或いは海運の不安定さや金属価格の高騰など、色々な要因を加味すると、最初からかなりシビアな値段設定だったからこそ、アッサリと白旗を上げたのだという判断はできると思う。
三菱商事の見積もり根拠がどんなものだったかは調べようがないが、恐らくは2021年時点では支那の風力タービンは結構安値で大量受注が可能な状況だった。これを船便で多数購入することでコスト圧縮し、建設もゴリ押しで短期間で対処か工場で概ね組み立てておいて搬送し、力業で設置みたいなやり方ならコスト圧縮が可能だったのだろうと。
したがって、ゴリゴリの安値で三菱商事が入札していたとしても、事業体としては日本近海で多数の風車を建てることでコスト圧縮するという目処が立たなくなったという可能性まで考えれば、「もう無理」は妥当なんだろうという評価をしている。
そして恐らくは、現状ではどの事業者が受注していたとしても入札額で黒字化は相当無理がある話なのではないか。
受注を逃した企業からは恨み節が漏れていても不思議はないんだけど、ね。

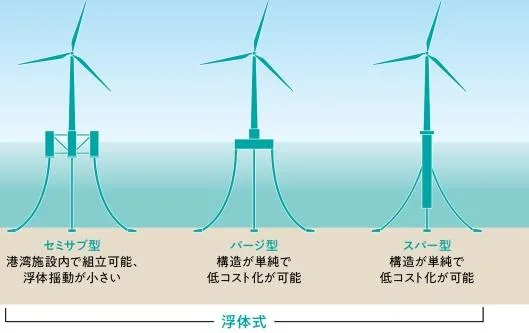


コメント
こんにちは。
>そもそも、「エネルギー安全保障」とか言いながら基本計画を書いたみたいだけど。
安全保障なんぞ飾りです。
エラい人には、それがワカランのですよ。
こんばんは。
飾りでも、真面目に考えて欲しいと願っていますよ。
余談ですが。
この件、旧ツイッターで
「ゴリゴリの安値で他社蹴り落として落札した挙げ句、コストとスケジュール過多で脱落とはこれいかに(怒)」
という意見を見ましたが、真相や如何に……
追記で書きましたが、三菱商事がかなりの安値で競り落とした可能性は高いです。
具体的な受注金額は不明ですが、論拠は追記で示した通り。
そして、スケジュールに関して、三菱商事は他者よりも長く設定されていたそうな。ですが、蓋を開けてみたら「見積もりが甘かった!」という結果に。
マージンが薄すぎたということはあると思います。が、だからといって他社が高値受注していたら成功出来ていたかというと、怪しいんですよね。