「もはや推進すべきものではない」で終わりだなこの話。
「メガソーラーは悪」のレッテル貼り 地域に根付く施設さえヤリ玉に 釧路湿原問題が再エネ全否定を招く危機感
2025年9月21日 06時00分
全国各地の大規模太陽光発電所(メガソーラー)事業に対する批判が強まっている。法令違反や環境破壊は看過できないが、太陽光発電自体は再生可能エネルギーとして推進すべきものではなかったか。環境に配慮しながら運営されるメガソーラーも含めて全て悪なのか。現場を訪れて考えた。
東京新聞より
流石、アジビラの本領発揮、東京新聞である。というわけで、久しぶりの東京新聞への突っ込み記事だ。
出来るだけ公平な視点を目指したいところだけれど、アジビラに対してやや批判的な視点から構成される点はご容赦願いたい。
営業記事は程々に
タイトルから既におかしい
タイトルからして、「地域に根付く」とか書かれているんだけど、紹介されているのは「市民エネルギーちば」の事例である。え?いつ根付いたの?文章からそんな話は読み取れないんだけど。
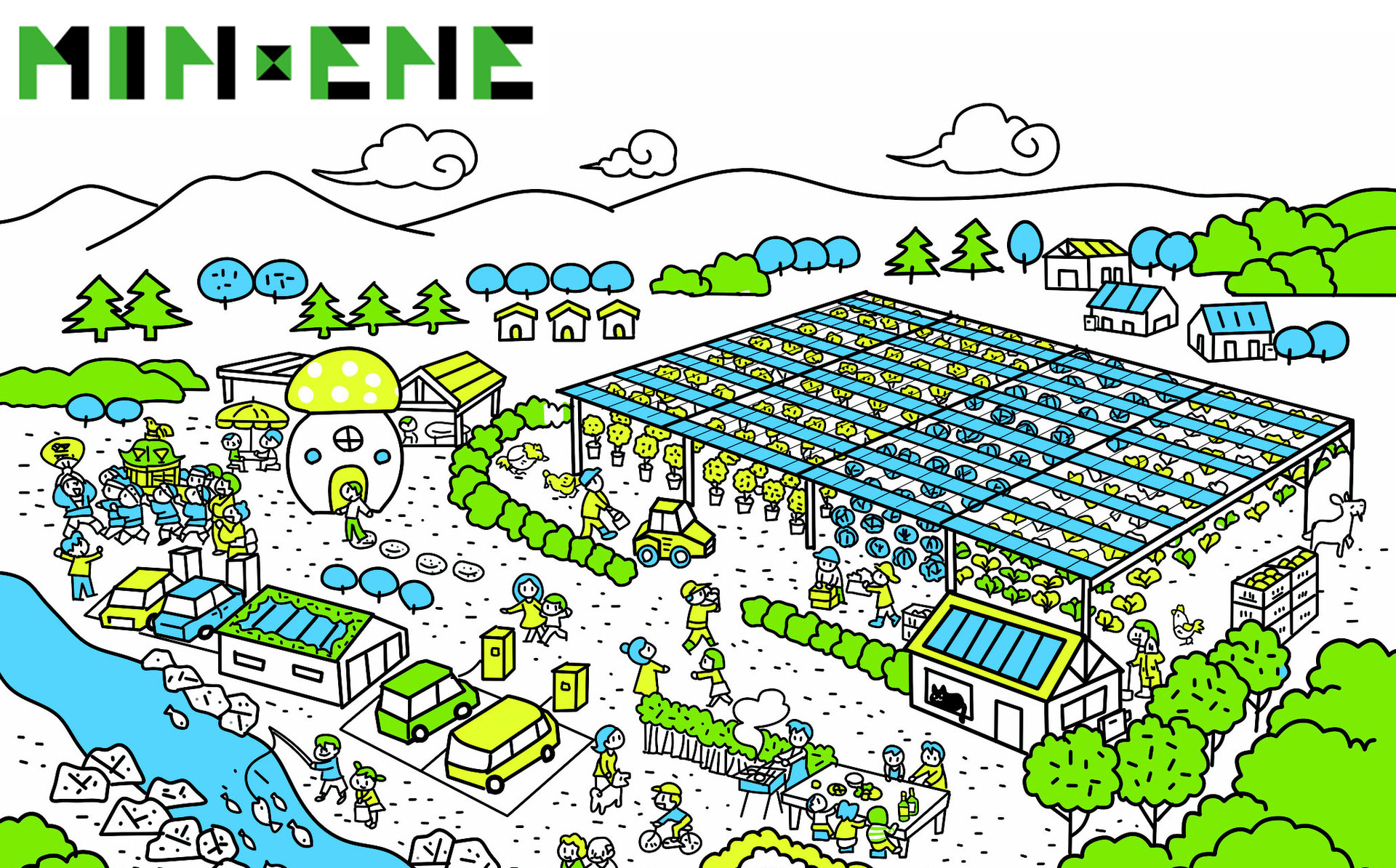
参考までに紹介されている事業体のサイトを見たらびっくり。なんだ、東京新聞の紙面で紹介している内容は、ほぼこの内容に沿った内容じゃないか。
大体、「市民発電所」って言葉自体が胡散臭いんだよね。真っ当な事業化は「市民」なんて言葉は先ず選ばないから。
とはいえ、「市民エネルギーちば」を批判するつもりはない。エシカル教育の推進などとおかしなことを言っているが、思想信条は自由なのだから賛同する人を批判するつもりもないのだ。そういう認識を持った仲間が集まった事業だと認識すれば不思議もない。
ただ、そうすると、どうやらこの記事は、「営業」された記事である疑いが出てきたね。
リード部分でも
> 全国各地の大規模太陽光発電所(メガソーラー)事業に対する批判が強まっている。
いきなりなんだけど、この部分、確かにネットを中心にメガソーラーに対する忌避感が広がっているのは事実だろうと思う。
でも、タイトルには「釧路湿原問題が再エネ全否定を招く危機感」って書いたのに、いきなり全国規模に話を展開してしまった。
そして、その文章を受けて、次のように続けている。
> 法令違反や環境破壊は看過できないが、太陽光発電自体は再生可能エネルギーとして推進すべきものではなかったか。
既にメチャクチャである。恐らく、「法令違反や環境破壊」は釧路湿原問題のことを念頭にしていると思われる。
全国各地の話を始めてこの文に繋げると、あたかも全国各地で法令違反や環境破壊が行われているかの如く読めてしまう。
そして、逆説的に「太陽光発電自体は再生可能エネルギーとして推進すべきものではなかったか」と問いかけているが、冒頭に突っ込んだ通り、そんなレッテルは既に剥がれてしまったのだ。
> 環境に配慮しながら運営されるメガソーラーも含めて全て悪なのか。
誰もそんなこといってねぇ!
記者には、精神に関する病気の疑いがあるので、是非とも病院に相談して欲しい。そうでないとしたら、完全に校正ミスである。
リード部分に必要だった内容
ニュースメディアであれば、事実を公正に伝えるための配慮が必要で、角度を付けた記事を書くのであれば、どの立場から見た内容かを明らかにすべきである。
だから、本来であれば、このように構成されるべきであった。
全国各地の大規模太陽光発電所(メガソーラー)事業に対する批判が強まっている。太陽光発電を推進する立場からは、釧路湿原で行われたような法令違反や環境破壊は看過できない。しかし、環境に配慮しながら運営される事業体まで悪者扱いすべきではない。
当ブログで再構成
とまあ、一事が万事こんな感じだし、途中から会員限定記事となっているので、以降は概略に対して突っ込みを入れるスタイルにしていく。
市民で発電所?!
ソーラーシェアリングの宣伝
まず、「市民エネルギーちば」がどういう業態なのか?をなのだが。
県内の環境団体の代表者らが2014年、「市民で発電所を建設したい」と考えて同社を設立した。衰退する地域農業の再生も目指し、耕作放棄地を活用している。パネルの下で農業法人が大豆と麦を育てている。
東京新聞より
東京新聞にはこのように報じられている。事業体の設立理由が「市民運動の一環」であることを明らかにしている点は好感が持てる。
ただ、ちょっと不可思議な記載もある。
市民や信用金庫などの出資を受けながら事業を拡大し、現在では23ヘクタールの農地にメガソーラー2基と1メガワット未満の通常の太陽光発電24基を稼働させている。
東京新聞より
一読すると23haの農地が1つあって、そこで営農型ソーラーをやっている風に読める。だが、メガソーラー2基とは、如何に?
一般的にメガソーラーとは、一般的に出力1メガワット(1,000キロワット)以上の大規模な太陽光発電設備を指す。
そこで調べて見たのだが、「市民エネルギーちば」は以下のような発電所を保有しているらしい。
- 匝瑳メガソーラーシェアリング第一発電所 :約1.2MW(3.2ha)
- 匝瑳おひさま発電所 :約2.7MW(6.45ha)
- 匝瑳第一市民発電所 :約35kW
- 匝瑳第二市民発電所 :約62kW
- 他、市民発電所多数
なるほど、メガソーラー2基というのは、「匝瑳メガソーラーシェアリング第一発電所」と「匝瑳おひさま発電所」のコトで、「1メガワット未満の通常の太陽光発電24基」は、恐らく24箇所で似たような業態をやっているという意味のようだ。
そうすると、記事からはハッキリ分からないものの、「市民エネルギーちば」は手広く電力事業を手掛けている実態が見えてくる。
デメリットも存在する
しかし、営農型ソーラーは、メリットもあるがデメリットもある。
本来、農地は農業以外の目的で使用してはならないという規定に縛られる。農業法人なのだから、それを厳格に守る必要がある。が、営農型ソーラーはそのルールの例外的規定で、ここで発電した電力は販売が可能となる。つまり、電力販売事業が主体となってはいけないが、農業の傍ら実践するのは許可されるというスタンスだ。
だが、農水省が説明するように、本来は自前で電力を消費することが前提になっていて、太陽光パネルの運用によって売電収益を得ることが目的とされてはいない。そして、「一時転用許可」であり、恒久的な取り組みとは違うのである。
実際、支柱を建てる必要があるため、農業機械との干渉を考えたり、日照条件と植物の育成のバランスなどを考えたりと、割と条件はシビア。
課題をまとめておこう。
1. 農業生産性の低下
- パネルによる遮光で作物の収量・品質が低下する可能性
- 作物ごとに必要日射条件が異なり、パネル角度・配置で調整が必要
2. 設備の維持管理コスト
- 農地に設置する鉄骨・架台・配線が農作業の邪魔になりやすい
- 草刈り・耕起・収穫機械の導入に支障
- 設備のメンテナンス(錆・ボルト・パネル清掃)が収益性を圧迫
3. 経済性の不確実性
- FIT(固定価格買取制度)依存で、買取価格が下がると赤字リスク
- パネル寿命(20〜30年)と農業の持続性が一致しない
4. 農地利用の矛盾
- 農水省は「営農継続が条件」としているが、監視・実効性に疑問。
5. 環境・景観への影響
- パネル下の生態系が変化(鳥獣・虫・雑草のバランスが崩れる)。
- 支柱・基礎の設置で土壌が締め固められ、水はけや地力に悪影響。
6. 災害リスク
- 台風・豪雪で架台倒壊。
- 高電圧を扱う為に感電リスクあり。
7. 地域との摩擦
- 「農業振興」名目で補助金・FITを得ながら、実態は発電事業
- 「農業軽視」「利益優先」との批判を受けやすい
災害時の対応
また、災害時の給電体制の話だが、ここもやや疑わしい。
災害時には発電を地域に開放しており、2019年の台風で停電が起きた際も6日間に延べ150人がスマートフォンの充電などに使った。
東京新聞より
コレの説明に写真も紹介されている。

なるほど確かに、災害時に無料開放しているようだね。ただ、調べて見るとその印象は最初とはちょっと異なる。
災害時の無料給電所
~~略~~
電力の無償提供は、あくまでも開畑地区を含む大規模な停電が発生した場合のみで、豊和村つくり協議会の管理の下で行われ、スマホや携帯、パソコンへの充電の他、AC100vで消費電力が1500wまでのあらゆる電気器具への電気の供給が可能です。現地に炊飯器を持ってくればご飯を炊いて持ち帰ることもできます。災害時には是非活用ください。
豊和村つくり協議会のサイトより
ああ、なるほどね。「大規模停電」に限定したには訳があって、太陽光発電って、停電しちゃうと売電できないんだよね。だから発電するだけで余った電力が出来ちゃう。それを無料解放しようという話なのである。
営農型ソーラーが認可される条件として、「停電時に自立運転ができる」という要件があるので自立運転型パワーコンディショナーを利用しているハズ。だから、停電時には残余電力がある状態なんだよね。
まとめ
というわけで、東京新聞の記事の内容に戻っていくわけだが、この話は最近何処かで見た話だよね。
左派と太陽光発電は結びつきやすいのかも知れないね。
結局のところ、「批判してくれるな」という意図はあれど、太陽光発電の問題点には一切切り込んでいないおかしな記事であることには変わりないのだ。
そもそも営農型ソーラーって、農家が自家消費して余った電力を売って良いというコンセプトだった。が、紹介されている業態は、方向性が全く異なる売電前提のFIT関連事業だ。
一般的な平地設置型のメガソーラーとは異なり、営農型ソーラーは農地転用の許可が得やすいという利点があり、更に補助金や助成金を受けるメリットが出る。ソーラー限定のおいしい事業でなのだ。土地活用の意味では農地としても使える点が優れてはいるが、優遇されるべき業態かは怪しいところ。
だから、少しでもネガティブイメージをバラ撒いて欲しくないというのが本音なんだろうね。批判が集まって実態が明らかになるのは、嬉しくないという。
結論として、メガソーラー・営農型ソーラーには利点もあるが、欠点もあるんだよ。それを「推進ありき」で推していくのは違うんじゃないかな。太陽光発電を批判するつもりはないけど、もう推進する時代じゃないんだよ。
追記
もう、そういう時代じゃなくなったよね。
太陽光発電の見直し焦点に トランプ関税踏まえ、自由貿易の意義強調も 自民総裁選演説会
2025/9/22 20:23
22日に告示された自民党総裁選の立候補者の所見発表演説会では、太陽光発電を始めとした再生可能エネルギー政策の見直しや、トランプ米政権の関税措置を念頭に置いた通商政策の在り方といった経済分野でも主張が繰り広げられた。米価高騰が収まらない中、農業政策に注力する訴えも多く聞かれた。
産経新聞より

この光景を見て「美しい」とは思わない。これが釧路湿原の周辺の実態らしいので、確かにちょっと異常だよね。




コメント
こんにちは。
>「メガソーラーは悪」のレッテル貼り
レッテル貼りはキミタチのお家芸じゃないかと小一時間>東京新聞
※望月イソコのあれやこれやはどうした?
>完全に校正ミスである。
「問題のすり替え」は、彼らのお得意の戦術、ミスリード上等というかむしろそれを誘う常套手段ですよね。
太陽電池自体は否定しないんですよ。
それを政闘の、あるいはなんらかの利益誘導の具とするのが許せない。
そもそも論として『既にそこにある原発』を再稼働すればエネルギー問題の大半は解決する、というのを意図的に隠すのも含めて。
こんにちは。
太陽光発電はご自分で使われる分には問題ないと思います。それで、発電した分電気代がお得になりますしね。
ただ、それを電力会社に高値で売って、その分を他の利用者が補填するという構図がどうかと思うわけでして、況してやそれが事業の一環となると。
更にその上に、営農型ソーラーは優遇措置が設定されているわけですから、そりゃ否定的にもなります。
そんなことより原発を再稼働しろというのは、全く以て賛成であります。
そもそも、民主党時代にソフバンのハゲ孫のいいように法整備されたのが元凶でしたっけ。
ピンからキリまで朝鮮・中華利権ですよね>ソーラー
そんなこともありましたね。
釧路市にはメガソーラーが250ヶ所以上あるそうですね。
まさに、太陽光利権の草刈り場といえるでしょう。
我が国のメガソーラーは、小泉珍次郎が環境相のときに推進されたのです。
特に、国立公園でのメガソーラー推進の犯人はコイツです。
国民はこのことをよく覚えておくべきでしょう。
「メガソーラー利権に群がった小泉と河野一家」
https://note.com/economymilitary/n/ndc65412dd7a4
かつては、釧路湿原は原野商法のメッカとして知られていましたが、今や安く手に入るのでしょうね。
そして、安く手に入る太陽光パネルで埋め尽くすと。
最悪ですよね。
ただ、小泉氏と河野氏が関わっているかは、僕自身は検証できていませんので、そこは評価を保留にさせて下さい。