ここのところ、この手のニュースが急に増え始めたね。
習近平の「鉄道崛起」は巨大なブラックホール、判明した負債は1兆4600億ドル
2025/06/25 08:03
過去およそ10年の間に雨後のたけのこのように増えた中国の都市地下鉄が、地方財政を圧迫する巨大なブラックホールになった…という報道が中国国内で相次いでいます。
朝鮮日報より
支那の鉄道事業がやばいことは何年も前から分かっていた話で、何故、今になってそんなニュースが色々出てくるようになったのだろうか?
最初から無理だというのは分かっていた
高速鉄道がもはや壊滅的
何度か触れている話で、端的な記事はこちら。
去年5月の記事だが、この時は高速鉄道の94%が赤字路線だったという話であった。支那高速鉄道は、北海道と同じで営業距離がやたらと長い割に利用客が少ないという問題があって、保線などには天文学的な維持費がかかる。
そして、こちらの記事でも触れたが、政治的理由でやたらと駅が作られる。にも関わらず利用者は増えないという悪循環である。
利用料金を上げるという話もあるのだが、かなり格安に設定している高速鉄道の値上げをすれば、金持ちだけしか利用できなくなってしまい更に収益性は悪化する。
本来であれば、都市間の高速移動などに使うか、貨物輸送のために鉄道を作れば良かったのだが、そうはならなかった。高速鉄道の建造技術は多少上がった為にインドネシアへの輸出を成功させるなど、成果がなかったとは言わないが、収益化するとは思えない。
未だに路線拡大の方針が掲げられているが、現状維持を続けても赤字を垂れ流すような状況なので、泥沼状態が続くのは避けられない。
地下鉄事業は
では、地下鉄は?というのが本日のテーマである。
昨年は深センで7.7兆ウォン(現在のレートで約8100億円。以下同じ)相当、北京で4.1兆ウォン(約4300億円)相当の赤字になるなど、経営実績を公開している28都市のうち26都市が大規模な赤字を出しました。29都市の地下鉄の負債規模も、2023年末現在で4兆3000億元(約87兆円)になりました。
朝鮮日報「習近平の「鉄道崛起」は巨大なブラックホール」より
当然赤字になる。
何しろ、首都北京の地下鉄ですら赤字垂れ流し状態なのだから、地方都市で黒字化するわけもない。その理由についてはこのように言及されている。
中国は、全国55の都市が地下鉄を運営していますが、このうち1キロ当たりの1日利用客数が1万人を超えて重要が十分にあるところは北京・上海など7-8カ所に過ぎないといいます。にもかかわらず、各都市は巨額の資金を投じて地下鉄を建設しました。
朝鮮日報「習近平の「鉄道崛起」は巨大なブラックホール」より
北京や上海は1日利用客が1万人を超えているとか、それでも赤字なんだそうな。
赤字体質になる理由
更に不穏な話が書かれているが、北京の地下鉄についてもう少し掘り下げよう。
中国26都市の地下鉄が巨額赤字に―香港メディア
2025年6月3日(火) 17時0分
2025年6月2日、香港メディア・香港01は、中国本土の26都市で地下鉄が巨額の赤字を抱えていると報じた。
記事は、重慶市で先月29日に公聴会が開かれ、05年の開通から20年間2元(約40円)だった地下鉄の初乗り運賃を3元(約60円)に引き上げる提案が示されたと紹介。この20年で営業距離が13キロから約500キロに拡大したのに伴い運営コストも増大しており、23年は総収入30億元(約600億円)に対して運営コストが111億元(約2200億円)に上り、政府補助金の約43億元(約860億円)を差し引いても巨額の赤字が残る状態に陥っていると伝えた。
RecordChinaより
実は、北京地下鉄の初乗り料金は3元(約60円:6kmまで)で、段階的に4元(6~12km)、5元(12~22km)、32kmを超えると20kmごとにプラス1元という価格設定である。東京メトロは6kmまでで170円の設定で、大阪が190円(3kmまで)、名古屋が210円(3kmまで)、ワシントンDCは距離にかかわらず最初の数駅が2.25USD(350円程度)なので、圧倒的に安いことが分かる。
なお、何れの地下鉄事業も赤字だった時代があり、運賃の値上げなど営業努力によって黒字化を果たしている状況にある。
当然、支那の地下鉄利用料金は激安設定なので、黒字化するわけもない。2014年12月まではどこに行くにも一律2元だったが、それはあまりにもということで運賃改定はなされた。でも、相変わらず格安で、かつ支那全土で似たような料金体系が維持されている。地域性すら加味せずに安値の営業運転を続けているのだ。
だが問題はそれだけではなく、今なお路線拡大を際限なく続けている状況なのが問題なのだ。当然、路線を伸ばせばそれだけコストがかかるわけで。
その上で、地下鉄の建設費用が1キロ当たり5〜10億元(約100〜200億円)かかると言われ、人件費の上昇に伴って日常的な運営コストも高まっていることが各地の地下鉄経営を圧迫していると伝えたほか、1日の旅客輸送密度を1キロ当たり7000人以上とする国務院の要求を満たしている都市はわずか17都市にとどまっていることを指摘した。
RecordChinaより
建設コストが延々増え続ける状況で、かつ運賃を格安に設定しているので、利益が出るわけがない。ただし、北京はそれでも首都であり利用者増加が継続的に見込めるからまだマシな状況で、上海をはじめとした地方都市でそれなりの人口密度を維持しているところですら、巨額の赤字を抱える状況は同じである。
そこに拍車をかけたのが不動産乱開発であり、採算の取れる見込みのない都市建設をやったばっかりに負債ばかり膨らむ始末。
中国の地方政府は、政府所有の土地を不動産開発業者に売ることによって財政の半分を賄います。地下鉄の路線を新設して駅勢圏周囲の土地を高く売れば十分だ、と考えたのです。ところが不動産バブルがはじけたことで、状況は変わりました。地方政府は土地売却収益の急減のせいで、ただでさえ財政状況が厳しいのに、地下鉄維持のために巨額の補助金まで支払わなければならない状況に直面しました。
朝鮮日報「習近平の「鉄道崛起」は巨大なブラックホール」より
ついには赤字に耐えられずに営業をやめるところもチラホラと。
報道が出始めた
というわけで、悲惨な状況を伝えたわけなんだけれども、こんな話はさほど珍しい話でもないし、今に分かった話でもない。
北京の地下鉄事故に関する記事だが、なかなか酷い事故だったようだ。詳しい状況の分析などは結局報じられず終わってしまったが、状況的には雪が降ってきた中、鉄道の地上区間でブレーキ関連のトラブルがあったということで。
しかし、日本の地下鉄であれば、まずこんなことは起こり得ない。自動ブレーキシステムなど安全に関わるシステムが導入されていることもあるが、何より天候の影響によって鉄道運行の停止が徹底されているため、早めに対処し、安全が確認されてから運行が再開されるからだ。
そのような運行をするためには、十分なリソースが必要となるのだが、おそらくはそこが支那地下鉄の一番のネックになっているのだと思われる。つまり、資金繰りが厳しいので安全面が疎かになっているということだ。
そして、北京の地下鉄ですらこれだということが問題である。
でも、そういった話は今までは殊更大きくは報じられなかったのだが、ここへ来てEVの話や二次電池の話。そして鉄道の話などが取り上げられるようになってきた。そして、これが尽く習近平氏が力を入れて推進した政策だったというところがポイントである。
やや陰謀論めいた結論に着地するのは申し訳ないのだが、最近似たような記事を幾つか書いた。
一つ一つはこれまで説明したので取り上げないが、これらの話がどこに繋がっていくのかというと、こちらである。
今年の夏か、秋頃までに習近平氏は失脚させられるのではないか?というシナリオが囁かれるようになったが、本格的にどうにも危うくなってきた気がして仕方がない。
追記
コレも関係する話なんだと思う。
中国共産党員が1億人超え、「給与」目的も多く
2025年7月1日 13:39 JST
ドナルド・トランプ米大統領が今春、国家安全保障上の理由から留学ビザの制限を開始した際、米政権は中国人留学生に照準を合わせ、中国共産党とつながりのある学生の入国を阻止すると断言した。
しかし中国では、共産党員であることが、特定のイデオロギーや習近平国家主席および同氏の対米挑戦に対する忠誠心と必ずしも結びつかない。むしろ入党は「鉄飯碗(政府や国有企業での安定した職)」を確保するための一歩と広く考えられている。
WSJより
WSJ記事なので、中身を読みたい方は会員になるのが良いと思う。
が、要は巨大な支那共産党の党員に対して、それなりの利益を配るために資金を用意する必要があることと、この体制を崩すことを恐れて積極的な動きが出来ないのが、今の習近平体制だよという話がしたいだけなので。
そして、恐らく習近平氏はこの支那共産党員からの支持というか、信仰を失っているんだよね。
追記2
な、なん、だと?
中国、デフレ圧力解消へ規制強化方針 習氏が党経済政策会議主宰
2025年7月1日午後 7:07
中国の習近平国家主席(共産党総書記)は1日、党経済政策機関となる中央財経委員会の会議を主宰した。国営通信新華社によると、デフレ圧力解消に向け、会議では国内企業による積極的な価格引き下げに対する規制を強化する方針が示された。
ロイターより
デフレ圧力解消、だと?!
通常、デフレ対策というのは色々あるんだけど、原因は以下のようなモノだ。
- 不動産バブル崩壊と信用収縮
- 消費者信頼感の低下(雇用不安、将来不安)
- 民間投資・輸出の伸び悩み
- 構造的な人口減・少子高齢化
恐らくはこれ以外にもあるんだろうけれど、一般的にはこの4つが問題として考えられる。そうすると、考えられる対策は以下のようなモノになる。
- 内需拡大策の強化 → バラマキ程度では一時凌ぎにしからない
- 不動産セクターの健全化 → 不良債権処理は支那共産党員の利益を毀損するので無理
- 地方政府の財政再建と支出の最適化 → 不動産開発の失敗に起因するので無理
- 企業活動の活性化 → 散々成長産業の芽を摘んできた
- 金融緩和政策の効果的運用 → 共産党の中央集権構造を破壊するので無理
- 国際環境への対応と輸出の安定化 → 共産党の中央集権構造を破壊するので無理
- 人口減少・高齢化への長期的対応 → これに成功した国家がないのでほぼ不可能
既に解消不能な状況になりつつあるのに、どうやってデフレ圧力に抗するつもりなのやら。
会議は「無秩序な低価格競争を仕掛ける企業は法規にのっとって規制されなければならない」と指摘。「企業は製品の品質を向上させ、時代遅れの生産能力を段階的に廃止するよう指導されるべきだ」とも強調した。
ロイター「中国、デフレ圧力解消へ規制強化方針」より
力で押さえつけて精神論で解決と。いや、無理でしょうよ。
結局のところ、習近平体制の維持が困難だけど、交代するには有力者がいないという現状で、経済や治安が非常に不安定化しているというのが、支那の実情なのだ。そうすると、仮に失脚が実現したにせよ、本質的な問題解決に至るには、内部崩壊か外に敵を求めるという2択になりそうな。タダでさえ、習近平氏の軍部への抑えが効きにくくなっていて、偶発的なトラブルが起きやすい状況になりつつあるのに、何とも不安なことだね。
追記3
おっと、「すごいもの」が出来上がったらしい。
わずか7秒で時速650キロまで加速、中磁気浮上技術が新たなブレークスルー―中国
2025年6月18日(水) 22時30分
湖北東湖実験室でこのほど、科学研究者は磁気浮上技術と電磁推進の方法を用いて、1.1トンの試験車両を1000メートルの距離内で時速650キロメートルまで加速させることに成功した。中央テレビニュースが伝えた。
極めて短い時間で時速650キロメートルまで達し、時速100キロメートルまで加速するのに1秒もかからない。その秘密はこの完成したばかりの長さわずか1000メートルの高速磁気浮上試験線に隠されている。
レコードチャイナより
100km/hに達するのに1秒かからないというのがどういうスピード(加速度)かというと、国内で最速のタイムをたたき出すバイクGSX1300R隼が、0ー100km/hで2.6秒、国内最速の市販車GT-R NISMOが0ー100km/hで同じく2.6秒。
世界最速の車(市販)は、現在のところ日本の会社である株式会社アスパークという会社が作ったEVのアウル (Owl)で、0ー100km/hが1.69秒(市販車)で、これは市販はされているけれどもスペシャルメイドカーなので参考になるかどうか微妙なところ。
ともあれ、プロドライバーがチャレンジするレベルの記録がこれなのだけれど、0ー100km/hで1秒弱だと3G近くの重力加速度が体にかかるわけで。全員前向きの座席に座ってシートベルトをして「耐える」レベルの乗り心地となる。
参考までにリニア鉄道の重力加速度が0.3G、新幹線は0.07Gである。また、富士急ハイランドに作られていたドドンパの加速度は3.75Gで、骨折する人が出たために廃止されてしまった。
そうか、新手のアトラクションを開発していたんだな?!



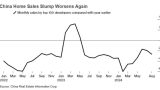






コメント
こんにちは。
「穴掘って埋めるだけでGDPは上がる」の真骨頂でしたからね>支那の鉄道網
需要など二の次三の次、ましてや(お金のかかる)安全などは……
こんにちは。
後は埋めるだけですね(真顔)。
冗談はさておき、後始末はどうするつもりなんでしょうね?放置するのかな。
誰が埋まるのかな?
まあ、どっちにしても、ここまで集金Pay!に権力集中させたんだから、ヤツの死と同時に地獄の釜が開きますね。
経済と跡目争いと、どっちが先に火を吹くか?
見物だけど、迷惑極まりない……
またまたご冗談を。
誰が埋まっているかは、掘って確かめようとしてはだめですよ。