そうなるとは思ってたよ。
中国、行き過ぎ「倹約令」迷走 会食で酒禁止、飲食業に打撃
2025年08月02日14時34分
中国の習近平政権による行き過ぎた「倹約令」が迷走している。もともと冷え込んでいた消費意欲がさらに低迷し、飲食業は大打撃。政権は早々に軌道修正を図る事態に追い込まれた。
時事通信より
習近平政権による「倹約令」が案の定、迷走している。もともと冷え込んでいた消費がさらに落ち込み、飲食業界は壊滅的打撃。政権は慌てて軌道修正に走る羽目になったという。
むしろ、景気が悪い時に倹約令を出すセンスが分からない。まあ軽めの話題だし、さっくり見ていこう。
- 経済低迷中の中国で「倹約令」が強化され、飲食業界が深刻な打撃を受けた。
- 地方政府の過剰反応で、ランチ禁止や罰金など意味不明な自主規制が横行。
- 指導部は軌道修正を試みるも、景気の冷え込みと自粛ムードは止まらず。
迷走する「指導」
飲食業関係者は苦戦
飲食業界の悲鳴は、今に始まったことではない。改めて言うまでもないが、支那経済は絶賛低空飛行中。アメリカとの関税交渉がややマシだったとはいえ、それはあくまで外向けの話。
アングル:デフレ下で価格競争激化、中国の飲食店に大倒産時代
2025年3月24日午後 3:25
中国の首都北京の郊外にある荒れ果てた倉庫で、中古厨房機器の販売業を手がけるアン・ダウェイさん(38)は飲食店向けの巨大な冷蔵庫と業務用コンロ、パン焼きオーブンの列を点検していた。
こうした機材一つ一つの背景に、倒産した飲食店の存在がある。アンさんは「一般人が飲食店を開くことは、ほとんど失敗が約束されたようなものだ」と話した。
~~略~~
しかし、2月の中国の消費者物価指数(CPI)は昨年1月以来のマイナスとなり、デフレスパイラルへの懸念を呼び起こした。
ロイターより
これは今年の2月の記事で、飲食店があっちこっちで倒産している北京の惨状を報じたものである。
昨年、アンさんらのチームは24年に毎月200軒の飲食店を解体し、前年と比べて3.7倍のペースとなった。中国の企業情報サイト、企査査のデータによると、24年に廃業した宅配企業は300万件弱と過去最高になった。
ロイター「アングル:デフレ下で価格競争激化~」より
昨年だけで、飲食店の解体は前年比3.7倍ペース。宅配企業も300万件近くが廃業した。倒産、閉店、撤退。
デフレ競争に耐えきれなくなって廃業したという風に分析されているのだけれど、まあ、こういった自体はさほど珍しくはない。

濃い赤が「nationwide restaurant closures:全国規模の飲食店の休業」で明るい赤が「nationwide restaurant openings:全国規模のレストランの開店」を示していて、開店している店も多いので、一概に厳しい状況だけとも言い難い。が、休業が圧倒的に増えているのが事態の深刻さを示す。
指導がトドメを刺す
とまあ、全体的な流れはそんな状況なので、更にその状況を悪化させるような政策をすべきではないことは、素人にだって分かる話。
そんな状況で、追い打ちをかけたのが「節約励行・浪費反対条例」の改正。
きっかけは5月中旬、習指導部が改正した「節約励行・浪費反対条例」だ。共産党関係者の腐敗防止を目指し2013年に施行された条例だが、今回新たに具体的な禁止事項を盛り込み、内容を厳格化。公務での会食相手に「高級料理やたばこ、酒類を提供してはならない」と明記した。
背景には、春ごろから地方の党幹部らの宴会で飲酒による死亡事故が相次いだことがあったとされる。このうち河南省では、綱紀粛正に関する学習会の翌日、公安や検察関係者も参加した集まりでアルコール度数の高い白酒を飲んだ1人が死亡。習政権の体面を汚す不祥事となった。
時事通信「中国、行き過ぎ「倹約令」迷走」より
習近平氏の方針である「虎もハエも叩く」を実現するには、腐敗を感じさせるような事態は改めねばならなかった。だから、宴会の飲食にブレーキをかけようとしたらしい。
しかし、おそらくは締め付けが厳しくなっている状況で、地方の党幹部らがその不景気な状況の憂さを晴らそうと企画した宴会だったに違いない。そこで箍が外れてしまった、そんな話なのだろう。
だが、そこで厳しく遣りすぎてしまうのが、支那のスタンダード。
条例改正後、地方政府や公的機関は連座制での処罰を恐れ、過度な自主規制に走った。報道やSNS投稿によると、安徽省では一部の公務員へのアルコール検査を連日実施。武漢の国有企業は同僚同士のランチを禁じた。
6月には、顧客に1杯6元(約120円)ほどの麺をおごってもらった銀行員が3000元の罰金を科された例が物議を醸した。3人以上での食事を避ける風潮が全国的に広まり、接待で定番だった高級白酒「茅台(マオタイ)酒」は深刻な価格下落に直面した。
時事通信「中国、行き過ぎ「倹約令」迷走」より
いやもう、何を楽しみに仕事をやれば良いのかという。
指導部、やり過ぎにようやく気づく
ようやく指導部も焦ったのか、6月中旬に「形式主義的な規制」を批判する論評を人民日報が掲載。
こうした過剰反応を受け、政権も火消しに乗り出した。6月中旬、党機関紙・人民日報(電子版)は「規定違反の飲食は禁止だが、全ての飲食が違反というわけではない」と題した論評を配信。「形式主義的」な規制を批判し、外食産業による景気や雇用への貢献を強調した。
時事通信「中国、行き過ぎ「倹約令」迷走」より
中途半端に、「全部駄目ってことじゃない」とか言い出したわけだが、じゃあ、何が良いんだ?という話になる。
しかし、社会の「自粛」ムードは続いている。香港紙・星島日報は7月、広東省広州の飲食業界で「閉店の波」が起きていると報じた。同省では条例改正直後に個室予約が8割減となったレストランもあり、夏以降も3割減の状態が継続。1人当たりの消費額も大幅に落ち込んでいるという。
時事通信「中国、行き過ぎ「倹約令」迷走」より
3月頃に飲食業界がかなり悲鳴を上げていたのに、何故か「自粛せよ」と指導したために、再びまた低調に。
泥沼にハマる
支那の経済対策は、泥縄というか、自縄自縛というか。最初から誰でも分かっていたはずの落とし穴に、なぜ毎回見事にハマるのか。
飲食業界は、消費の末端であり、庶民の気分のバロメーターでもある。そこを締め上げたら景気が死ぬのは当然の話。
「倹約令」で失われたのは、金だけではない。小さな楽しみと、ささやかな活気だった。
嫌気感が社会に蔓延すると、弱者にしわ寄せが来る。

日本人にまた被害者が出てしまったようだが、そろそろ日本政府も「渡航禁止」の勧告を出すか、それを出せないまでも警告するようにしたほうが良いよ。確実にこれから更に悪化するから。


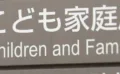

コメント
こんにちは。
「元の濁りの田沼恋しき」
ですなあ。
やる事にセンスないのは、共産主義政権の特徴ですね。
※その意味だと石破政権は共さうわなにをするくぁwせdrftgyふじこlp
こんにちは。
まさに、田沼意次先生をお呼びしなければ。
何というか、共産主義政権ならもっとドッシリ構えて良いように思うんですけど、どうしてそうはならないのか。
石破氏は(ry
プーチンが特別軍事作戦のマイクロマネジメントでgdgdになった様に
習近平もマイクロマネジメントでやらかす
トランプも関税でマイクロマネジメントしている
トランプだけでもソフトランディングしてくれないかな、無理だろうけど
独裁者がマイクロマネジメントに手を出し始めたら、全てが回りませんよね。
方向性を決めることができる独裁者が末端の政策に口出ししてはいけないのです。
トランプ氏も最前線に立って交渉したい!俺が一番巧くガンダムに乗れるんだ!というような。え?違う?
横合いから失礼します。
>トランプ氏も最前線に立って交渉したい!
それってどんなモンティ@モントゴメリーですか……
支那経済の危機的状況は長らく続いてきたけど、経済規模がでかく、当局が数字を隠蔽・改ざんしてきたため、どこまで逝っているのか、支那の実体経済の様相は観えずらかった。
ようやく支那政府自体が経済失政(破綻)を認め始めて、いまや失業者4億人とさえいうアナリストがいる始末。
失業してアルバイトしても月収600元(≒1200円)程度で、飯はカップラーメンや3元朝食、家賃やローンが払えず住まいを追い出されたり、貯金が底をついて路上生活する人民が増えていると。都市洪水と農村旱魃が頻発している中で生きているのか? 先般、北京を襲った大洪水でも、わずかに死者30人?
どこまで真実かはまだ不明ながら、支那の総人口は9億人またはそれ以下という話が国内外で拡散されていて、恐らくはそれも当たらずとも遠からずで、まともな人なら、支那の再興はムリ筋という認識でしょう。
数字を見ても実態が分からないのが支那経済の厄介なところ。
漏れ聞こえてくる情報を統合して、何となくこんな感じではないか?と推察するのが関の山という感じですかね。
ご指摘のように、洪水による被害者数も死者数は現状44名という風に報じられていますが、本当かどうか?死者数はともかく行方不明者が少なすぎる気がしています。単に把握していないだけの可能性の方が高そうですね。
ともあれ、匿名の方が指摘されるようにマイクロマネジメントの失敗というのが顕著に出た事案であるとは思っています。