支那経済不調を示す話なんだけど、ローン滞納か。
2500万人超がローン滞納の罠
2025年9月23日
新型コロナウイルスのパンデミック以降、中国経済は低迷を続け、消費と雇用の両方が大きな圧力にさらされています。中国政府は相次いで消費刺激のための特別政策を打ち出していますが、その効果は限定的です。多くの家庭は住宅ローンを返済しながら日常生活を維持しなければならず、借金に頼らざるを得ません。
VISION TIMESより
2,500万人滞納って数字は大きく見えるのだけれど、支那経済を支えるのは凡そ7億人ほどだと言われている(人口は公称14億人だが)。
流動性の罠が待ち構える
7億人が支える経済
支那の国家統計局の出す数字を信用するのは、ちょっと危険な気はするのだが、傾向は信用して良いだろう。
中国の就業者数、過去3年で4100万人余り減る-退職者急増が影響
2023年3月2日 20:03 JST
中国の就業者数は過去3年で4100万人余り減った。新型コロナウイルス禍と生産年齢人口の減少が影響している。
国家統計局によれば、2022年の就業者数は約7億3350万人。19年は7億7470万人だった。退職者の急増を反映するデータとなっており、定年引き上げという不人気の政策を政府が急ぐ可能性もある。
Bloombergより
情報がやや古いのだが、2023年の就業者数は7.3億人。武漢ウイルス感染症の直後の数字ではあるが、経済状況はあまり宜しくないことを考えると、恐らくは現在も7億人程度は就業者がいると想定して良いのではないかと。
2024年までの情報で、就業者数が減り続けているからね。
ともあれ、ローンの返済が焦げ付くということは、金融機関から融資を受けられる人ということになるため、大半は就業している方々の問題と捉えるべきだと思う。
で、デフレで失業者数が増えていることを考えると、約2,500万人くらいが(失業率5.3%、都市部労働人口5億人で概算)収入がないような状況だと想定されるので、2,500万人がローン滞納って話は大げさってわけでもない。
なお、簡単にローンを借りられるシステムみたいなので、収入がない方もローンを借りている可能性もあるが、それを論じるのは難しいのでそれはさておく。
消費者信用の拡大
で、ローン滞納者が増えると言うことは、銀行の運営にも影響が出るという意味だ。これは7月の記事なのだけれど、不良債権問題もあってかなり銀行が苦戦しているのだとか。
中国の銀行、消費者信用拡大で苦戦 不良債権抑制と「板挟み」
2025年7月14日午前 7:41 GMT+92025年7月14日更新
中国の銀行が、消費者信用の拡大を図る新たな政府指針の順守に苦戦している。個人向け融資のデフォルト(債務不履行)が急増し、家計が健全で借り入れを希望している世帯を見つけるのが困難な状況が要因だ。
ロイターより
なかなか重苦しいタイトルのニュースだが、具体的な数字があるわけではない。ただし、支那の政策金利は1年ものLPRが3%、5年ものLPRが3.5%となっていて、市中金利はそれより大幅に低い1.5%程度の設定の所もあるようだ。
にもかかわらず、流動性は改善していない。
中国人民銀行、成長政策支援の強化を約束
2025年9月26日午後9時39分 GMT+9 2025年9月26日更新
中国人民銀行は26日、「複雑かつ厳しい」外部環境の中、経済成長を支えるため金融政策の調整を強化し、金融政策と財政政策の連携を強化すると発表した。
~~略~~
中央銀行は、潤沢な流動性を維持し、金融機関に信用供給を増やすよう指導し、債券市場、特に長期利回りの変化を注意深く監視することを約束した。
ロイターより
支那の銀行はそもそも現在、現金を保有していない。不良債権を大量に抱えて、その処理のために汲々としているからである。
中国四大銀行、稼ぐ力最低に 不良債権処理に懸念で公的資金注入も
2025/9/2 19:30
中国の四大国有銀行が長引く景気低迷で稼ぐ力に衰えが見え始めた。2025年1〜6月期連結決算は本業の預貸業務で得る「利ざや」が08年のリーマン・ショック後で最低水準に縮小し、当時と比べ半分以下に落ち込んだ。不動産業界で発生する不良債権を段階的に処理するものの、中国建設銀行と中国銀行は原資が足りなくなる事態に備え、政府が公的資金を注入した。
日本経済新聞より
流石に原資が足りなくなっては困るので公的資金注入を行う話にはなっているのだが、これは根本的な解決に至らず一時凌ぎである。
今の支那は完全に「流動性の罠」に陥った状態であるといえそうだ。
流動性の罠
流動性のワナ(Liquidity Trap)とは、金融緩和により金利が一定水準以下に低下した場合、投機的動機による貨幣需要が無限大となり、通常の金融政策が効力を失うことを指す。金利水準が異常に低いと、いくら金融緩和を行っても景気刺激策にならない状況に陥るのだ。
支那は、本当であれば金利引き下げをすることでなんとかこの状態を回避したいのだが、政策金利は人民元防衛のために下げることが難しい。資本流出を引き起こしかねない事態だからである。
「公積金」利用の不安
それと、見逃していたニュースとしてこんな話があった。
中国、住宅市場支援で「公積金」活用-約220兆円規模の積立金制度
2025年6月10日 11:07 JST
中国は住宅市場の活性化を図るため、これまであまり注目されてこなかった10兆9000億元(約220兆円)規模の資金プールを活用し始めている。銀行ローンに代わる選択肢として国民に提供されている「住宅公積金」と呼ばれる政府の積立金制度だ。
~~略~~
中指控股の陳文静リサーチディレクターは、「依然として住宅市場に対する圧力が続いており、多くの地方政府がこの制度を活用して住宅ローン負担の軽減を図っている」と指摘。「住宅市場を支える政策の中でもトップランナー的な存在だ」との見方を示した。
Bloombergより
「銀行ローンに変わる選択肢」などと書いているが、「住宅公積金」は労働者が将来の住宅購入に備えて積み立てる制度である。いくら11兆元規模の資金がプールされているからと言って、ここに手を付けるのはかなりリスキーだ。
何故なら、本来使うべき人々の為の資金が枯渇してしまうと、実際に積み立てた人々から文句を付けられかねない。場合によっては暴動に発展しかねない。……あれこれ、今の日本の社会保険制度とあまり変わらないような。
いやそれはともかく、11兆元規模の資金は潤沢に見えるけど、地方政府が抱える不良債権総額は40兆元を遙かに超えるといわれているので、全額溶かしても足りない可能性が高いのだ。
繋ぎとして使うのは「乗り切れる場合」に限られる話なんだけど、そもそも不動産絡みの不良債権は時間が経つにつれて状況が悪化するんだよね。
まとめ
あれこれと悪材料を並べてしまったが、支那の銀行が破綻するような事態になると、日本経済にも悪影響が波及してくる懸念がある。
そもそも抗日映画を使って不満を逸らすことを画策する時点で、色々と間違っているというか手遅れなんだよね。
そんなわけで、冒頭のニュース「2,500万人滞納」って数字は、「VISION Timesでしょ?またまたご冗談を」という反応を引き起こす話に見えて、その実、実情を掠っていくと寧ろ過小評価の可能性すらある。
一方、日本企業にとって支那との経済的付き合いを今後も続けると言うことは、地雷原でタップダンスを踊るようなものだ。できるだけ早く、手仕舞いするように動いていかなければならないだろう。

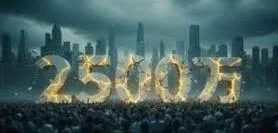


コメント
こんにちは。
>地雷原でタップダンス
言い得て妙ですなぁ……
平気で核地雷埋めてそうですが。
こんにちは。
核地雷って、それは四方数kmを吹き飛ばしそうですね。
でも、実際そちらの表現の方が正しいかも?