EVへの補助金打ち切り方針を発表した裏で、こんな事態が起きている。
中国BYD株下落、減収減益決算-国内EV市場の競争激化で苦戦
2025年10月30日 22:24 JST 更新日時 2025年10月31日 13:37 JST
中国の電気自動車(EV)メーカー、比亜迪(BYD)が30日発表した7-9月(第3四半期)決算は、減収減益となった。国内市場で競争が一段と激しさを増すなか、業界への厳しい視線も強まり、販売見通しに下押し圧力がかかっている。
Bloombergより
BYDの業績悪化は今年の春から鮮明になってたから、この結果は仕方がない面はあるよね。
EV産業、補助金打ち切りで転換期へ
補助金による後押しを失うEV産業
ええと、先ずはこちらの記事のリンクを。
この記事は4中全会で経済へのテコ入れが低調だったよ、残念だね、という内容である。で、そこで問題視したのがこちら。
焦点:中国のEV産業、市場競争で一段と強く 政府支援打ち切り
2025年10月30日午後 7:08
中国は電気自動車(EV)産業への政府助成を打ち切る姿勢を鮮明に打ち出している。
今月の中国共産党第20期中央委員会第4回全体会議(四中全会)で基本方針が決まった「第15次五カ年計画(2026-30年)」で、EVは過去10年余りで初めて戦略的な新興産業のリストから除外された。
ロイターより
EV産業が、熟成産業ねぇ……。ここ1~2年でようやく軌道に乗った感じなのに、成熟するの早いな。
補助金に依存して成長してきた産業構造が崩れるタイミングとしては、正直あまりに早すぎる感がある。
値下げ競争勃発
実際、既に随分と熾烈な値下げ競争を繰り広げている。
EVとプラグインハイブリッド車(PHV)を合わせた販売台数は115万台で、前年同期比1.8%減少。一方、競合する浙江吉利控股集団(ジーリー)と重慶長安汽車は第3四半期の販売台数が前年同期比でそれぞれ96%増、84%増となった。
世界最大のEVメーカーであるBYDは、中国市場での首位維持をめぐり、厳しい競争を強いられている。値下げ競争が過熱し、行き過ぎた競争が品質低下を招くおそれがあるとして、中国政府内では懸念の声も広がっている。
Bloomberg「中国BYD株下落、減収減益決算~」より
ここから分かることは幾つかある。
- 自動車産業はEV・HV・エンジン車問わず、製造工場を維持する固定費が重い
- BYDは補助金で固定費を補填する構造だった
- 今年の「走行距離ゼロ中古車騒ぎ」は、このバランス崩壊の象徴
共産党指導部も、この経済モデルの脆弱性を重く見たはずだ。
「走行距離ゼロ中古車」の騒ぎは、以前もこんな感じで触れたね。
当然ながら、共産党指導部もこの事態は重く見ていただろう。
特にBYDは自前のサプライチェーンを強化してコストダウンを進めてきたため、自分で抱えている負債も巨額である。
車に例えるなら、ボディは工場、補助金はタイヤ。タイヤを失えば、まともに走れなくなるのは自明である。
バフェットが手仕舞い
なお、こうした兆候は既に夏頃には見えていた。
無名の中国企業から「バフェット銘柄」に。バークシャー、出資17年でBYD株を全売却
2025年10月4日
米著名投資家ウォーレン・バフェット氏が率いる投資会社バークシャー・ハサウェイが、中国自動車大手BYD(比亜迪)の株式を全て売却したことがこのほど明らかになった。
~~略~~
その後もバークシャーはBYD株の売却を継続。2024年6月には出資比率が5%以下にまで下がっていた。最近提出した資料で、3月末時点でBYD株の保有がゼロになっていたことが判明した。
36krより
投資家の手仕舞いも進み、BYDの業績悪化に対する懸念は株価にも反映されている。
31日午前の香港市場で同社の株価は一時6.4%安を付けた。
7-9月の純利益は前年同期比33%減の78億2000万元(約1700億円)。売上高は同3%減の1949億8000万元と、市場予想の2160億元を下回った。
Bloomberg「中国BYD株下落、減収減益決算~」より
冒頭に紹介した記事でも投資家が手仕舞いを始めている様子が見て取れ、既に好調さに陰りが見え始めていた所に、更に4中全会の追い打ちがあったことで、今後さらに苦境に立たされる可能性は高そうだ。
業界全体に波及
問題は、BYDの体質云々ということだけではなく、自動車を製造している関係企業に大きな影響がもたらされる可能性が否定できないことだ。
不動産開発業の時も、恒大集団が倒れ、碧桂園がどうにもならなくなって、今後もこの状況は加速すると言われている。EV産業は更に裾野が広い産業なので、電池産業から部品製造産業、更に半導体産業まで影響を及ぼす可能性は高い。
コラム:中国自動車業界、破滅への疾走 危機招く構造問題
2025年9月6日午後 3:13
中国の自動車業界は、外部から見れば破竹の勢いに見えるだろう。
~~略~~
必要とされる2倍もの生産能力や、他の固定費を抱えることは財政的な流出要因となる可能性がある。皮肉なことに、これは自動車メーカーが市場シェアを持続的に拡大するというほとんど無駄な希望の下で、ますます多くのインセンティブを提供するという悪循環を招き、損失を悪化させている。
ロイターより
このコラムがかなり分かりやすい説明がなされているのだが、経営破綻、人員削減の流れは避けられないだろう。
レアアースを巡る動向
オーストラリアが増産へ
話は少し変わるのだが、こんなニュースが伝えられている。
双日、オーストラリア産レアアース初輸入 中国依存脱却へ一歩
2025年10月30日 5:00
双日は30日までにオーストラリア産の希少レアアース(希土類)を初輸入した。電気自動車(EV)や風力発電機向けモーターなどに必要で希少性が高い「重希土類」を中国以外から輸入するのは日本で初めて。今後、国内需要の3割程度を調達する。中国がレアアースの輸出管理を強める中、中国外の資源確保は日本の経済安全保障に直結する。
日本経済新聞より
ここのところ、複数の国でレアアースの採掘などが計画されていて、オーストラリアなどは日本やアメリカと組んで積極的な輸出を目指す方向性であるようだ。
それというのも支那が圧倒的なシェアを誇るこの分野の影響を排除していこうという力学が働いているためである。
海洋資源の活用ができれば更に状況は変化
更に、何年もトライしながらなかなか実を結ばない海洋資源開発も、これを機にもう少し積極的にやろうという方針が見えてきている。
期待が強まる国産レアアース。南鳥島沖に眠るレアアース泥の開発は「中国依存」脱却の切り札になりうるが、壁は高い
2025/10/22 9:00
国産レアアース開発への期待が強まっている。日本の排他的経済水域(EEZ)内に、埋蔵量世界3位となる約1600万トンのレアアースが眠っているとされるのが日本最東端の南鳥島(東京都)周辺の海底だ。2013年、海洋研究開発機構(JAMSTEC)や東京大学などの共同調査で、水深6000㍍の深海にレアアースを高濃度で含む「レアアース泥」が発見されたのがきっかけだ。
東洋経済より
この手の資源開発のほとんどのケースでは、空振りに終わることが多いのだが、続けることに意味があるし、成功すれば高コストであっても採掘可能な「鉱山(海底だが)」を持っているだけで意味がある。
アメリカとしても、他にも色々と手を打ってはいるようだ。

日本、マレーシア、タイ、ヴェトナム、カンボジアと合意を結んだアメリカは、今後、レアアースの採掘を模索していくことになるだろう。
一応の妥結
尤も、首脳会談においてリスク回避に成功したと伝えられている。
中国がレアアースの輸出規制強化1年延期、アメリカは対中追加関税10%引き下げ…米中首脳会談
2025/10/30 20:42
米国のトランプ大統領と中国の 習近平シージンピン 国家主席は30日、韓国・釜山で首脳会談を行った。中国商務省は会談後、レアアース(希土類)の輸出規制強化を1年間延期すると発表した。これに対し、トランプ氏は合成麻薬フェンタニルの米国流入を理由とした対中追加関税を10%引き下げる方針を示し、世界経済を混乱させる米中の貿易摩擦はひとまず緩和することになった。
読売新聞より
とはいえ、こんな話はアメリカにしても一時凌ぎにしかならないことは明白。だからこそ前述したように手を尽くしているのである。
一方の支那としてはカードを切った以上は有効に使いたかったようだが、いまいち弱気であったようだ。
それもそのはず、EV産業の脆弱性が明らかになって、早急に他の産業を立ち上げねばならない状況なのだが、下手すればレアアース貿易という強力なカードを自ら失いかねない事態を迎えているのだ。
つまり、国内のEV産業が頓挫することで、レアアースの消費量も一気に落ち込む可能性が出てきた時に、世界にも売らないという戦略は、貿易面から考えてもマイナス。今は経済的に見ても外貨の欲しい局面なので、外貨獲得手段を不用意に失うわけには行かないという判断も出てきたということ。
まとめ
支那経済はこのように転換期に来ているのだが、しかし先に伝えたように4中全会では目立った方針を打ち出すことにも成功できなかった。
しかし、EV劣勢を見るに、補助金打ち切りをやって体質を改善しないと、不動産開発業の二の舞いになりかねない。レアアースも政治カード化していたが逆効果になりかねない事態である。
- BYDを含む中国EV産業は補助金撤退で転換期
- 裾野が広く固定費が大きいため、倒産連鎖のリスクが高まる
- レアアースは出口確保優先で政治カード化の逆効果を避けた
一連の流れを見ていると、ゴリ押しだけで経済成長というのが無理になってから、方針決定に苦慮している様子がうかがえるね。


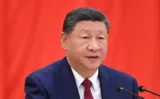



コメント
エビデンスはないですが、自動車業界の友人が言うには、全体の趨勢は(B)EVからPHEVだと。
世界市場でのEV総販売数は、2024まで堅調に増加してきました。
しかし、2025からそのトレンドが変わるんじゃないかとみんな推測しているそうです。
バフェット氏はそう考えたんでしょう。
少し前、つべを観ていたら「BYDは、Burn Your Dreamsだよ」なる支那人のコメントがあって、支那人はユーモアがあるなw、と思った次第。
PHEVですか。
あまり増えませんよね、日本国内でPHEV。車種が増えないのも理由かもしれませんが、価格が高くなりがちなのもその理由かもしれません。
もうちょっと、電池を小さくしても良いかもしれません。
BYD、燃える位で済めば良いんですが。
こんにちは。
>巨大産業のタイヤが外れた
この事故のことかと思いました。
https://x.com/hoshusokuhou/status/1983756127293878724
「【中国すごいよ】中国大手自動車メーカー・吉利汽車(ジーリー)の新車、ディーラーから納車された直後に前輪の足回りまるごと外れる」
BYDは比較的マシな方ですし、既存メーカのくびきにとらわれない意欲的な取り組みも色々やってます(前回モーターショーじゃなくてJMSでの『EV信地旋回』とか)が、補助金頼りの部分は全てのEVメーカが拭えない所でしょう。
これから地獄の生き残り合戦が始まりますが、それって『蠱毒』ですよね……
最強の毒虫が誕生しないことを祈ります。
※つまり、みんな死んでしまえ。
こんばんは。
そういえば、そんな事故もありましたね。
BYDはそれなりのノウハウが溜まっているのでしょうが、今の規模の生産力を抱えたまま、利益を出せる体質になるのかがポイントでしょうね。
蠱毒EVは結構強そうですね!