本日のコラムは、タイトル通りの与太話なので、その辺りを先ずはご了承頂きたい。
さて、本題に入る前にウクライナ情勢の近況を。
状況は日々変化していて、最近は航空勢力での駆け引きも活発だ。地上の戦線が膠着しているので、航空勢力での状況を覆そうという意図が感じられる。
ロシアがポーランドやエストニアに領空侵犯を繰り返すのは、NATOに対して「支援をやめろ」と圧力をかけるパフォーマンスにほかならない。
では、もしロシアが侵攻しなかったら世界はどう変わっていたか?本日はそんな思考実験である。
侵攻しなければ安定維持は可能だった
思考実験のルール
最初に、この思考実験のルールだけ明確にしないとダメだね。
前提
- ロシアは2014年のクリミア侵攻をしなかった
- ロシアは2022年のウクライナ侵攻をしなかった
今となっては考えにくい話ではあるんだけど、この2つの前提に基づいた思考実験である。
戦争回避シナリオのウクライナ
ロシアが侵攻しなかった場合、ウクライナはEU加盟・NATO加盟を目指して改革を進めただろう。実際、2014年のクリミア危機前からEU連携を深めており、2022年の加盟申請も「侵攻前から準備していた」と見るのが自然だ。
資本流入と規制適合によって経済は活性化し、国民に「自由で豊かな民主的社会」が現実にあることを示す。これはロシアにとって最も恐ろしいシナリオだった。
ゼレンスキー退場と民主化経済
ただし、ウクライナ大統領のゼレンスキー氏の政治手法は、戦争が開始する前は地に落ちていて、果たして任期満了の2024年5月まで政権を保てるかすら怪しかった。よって、少なくとも再選は考えられず、戦争回避シナリオでは、民主主義寄りの大統領が登場する可能性がある。
そして、EU統合や市場改革を更に推進することで、ウクライナの市場活性化した可能性は高い。
ただし、ウクライナの問題は今も昔も汚職問題であり、汚職問題と法の支配の強化が実現するためには、長い時間を要した可能性はある。EUに参加するためにはその条件をクリアする必要があるので、恐らく、2025年になってもEUに参加できていたとは考えにくい。
それでも、汚職撲滅や市場改革が前進していれば、ロシア国民にとって「民主化しても国は回る」という成功例を見せるに値する十分な心理的インパクトになっただろう。
尤も、そもそもクリミア侵攻がなかった世界線に、ウクライナ国民の腐敗への嫌悪感が高まったかどうかは不明。そうすると、2019年の大統領選挙で、ゼレンスキー氏が大統領になったかどうかも怪しいのだが、そこまで考えてもね。
ロシア政権への心理的リスク
一方、プーチン氏にとっての本当のリスクは経済的損失ではなく、民主化国家の成功例が近隣に存在することだった。
- 「ウクライナのEU・NATO加盟の可能性が差し迫っている」と強く警戒していた
- 「ウクライナは独立国家ではない」という独自の歴史観を強めていた
- ウクライナ国内の民主化へ向かう政権が受け入れられていないという誤解
- 親西側・反ロシアの民衆蜂起(カラー革命)の再来を恐れていた
- 国内支持率の低下
こうした不安を抱えたプーチン氏が、戦争を仕掛けない世界線でも、それに変わるインパクトのある行動を起こした可能性が高い。グルジアやモルドバ、ベラルーシなどに軍事侵攻していたシナリオは十分に考えられる。
アメリカの大統領選挙に影響
ロシアがウクライナに侵攻しなかった世界線では、トランプ氏の当選が実現できたかどうかは怪しい。
2016年の大統領選挙では、ロシアがトランプ氏の当選を後押しするような情報操作があったことが確認されている。一報で、クリントン陣営には不利益な情報が暴露された結果、信用を失った。
クリミア侵攻は2014年。2年後の選挙への影響はかなり色濃くあり、トランプ陣営当選に貢献した可能性がある。つまり、アメリカ初の女性大統領誕生により、トランプ氏は選挙に負けて大統領にならなかったかもしれない。
コレが波及して、以下の可能性もある。
- アメリカと支那との経済戦争が後回しに?
- 支那の不動産バブル崩壊のトリガーも先送りの可能性
- シリア内戦は沈静化してアサド政権は存続していた
- イスラエルの動向も今とは違っていた可能性がある
- アフリカにロシアの影響が拡大していた
この辺りになってくるともう、複数の事象が絡まりすぎるので、あくまで可能性の話なんだけどね。
防衛概念について大きな影
欧州に大きなインパクト
さて、現実の世界線では、ヨーロッパ諸国は軒並み防衛費を上げている。
- ドイツ、冷戦以来の「再軍備」へ本腰 国庫開く基本法改正―ロシア抑止で米頼れず
- スウェーデンがNATOに加盟した理由 – スウェーデンの外交・安全保障政策におけるパラダイムシフト
- ポーランド、国防費GDP比4%の憲法明記を検討
- デンマーク、女性も徴兵対象に 安全保障懸念高まり防衛力強化
- イギリスが防衛費拡大、2027年までにGDP比2.5%に 英米首脳会談前に発表
各国ともに防衛費の引き上げを表明していて、これはトランプ政権への対策という側面もあるのだけれど、ロシアの脅威の高まりを肌で感じていることで国民も反対しないという実情を反映したことだと思う。
日本も遂に重い腰を上げる
それどころか、世界に冠たる平和ボケ国家であった日本も、流石に防衛費の見直しを始めた。更に環太平洋地域としてはオーストラリアも、アメリカにせっつかれて方針の転換を図った。
日本もオーストラリアも、防衛費の引き上げにはかなり渋い国家だったけれども、オーストラリアはタブーにしていた原子力機関を搭載した兵器に手を出そうとしてAUKUSの締結を決断(なお、AUKUSは2021年締結で支那の海洋侵出に対抗する目的で締結しているが、遠因にクリミア侵攻があると考えられている)。
また、ニュージーランドも防衛費を増やす決断をした。
このような防衛力強化の後押しをしたのが、ロシアのウクライナ侵略であった。
ドローン戦略の高まり
また、戦略も大きな転換を図ることを強いられることになる。
ドローンの利用に関しては、中東でもかなり積極的に用いられていたし、記事にある様にナゴルノ・カラバフ紛争などでもその有用性を示していたため、多分、戦争が行われなくても運用は進んだのだろうけれど、前線での有用性を実戦で示したことは大きかったと思う。
特に、光ファイバードローンという、運用には不便だと思われていたドローンが、戦術上ではかなり重要であることが判明。これまでの常識を覆すような話も幾つか出ていて、恐らく侵略を行わなかった世界線とは異なる軍備の方向性になっていると考えられる。
もっと「平和」だった可能性
というわけで、欧州の軍備に大きく影響を与え、日本を始めとした環太平洋諸国にも軍備の必要性を示してしまったロシア侵略戦争は、始めなければもっと世界が「平和」だった可能性は否定できない。
尤も、何が「平和」だと定義すべきか?と言う問題はあって、寧ろ軍備を整えていた方が安心感は高いのかも知れないが、とにかく侵略戦争が世界中に危機感を与えたことは間違いない。
「世界には、こんなヤベー国が未だあるんだ」という事実を知らしめたのである。
まとめ:歴史上のifを考える
というわけで、侵略戦争が起こらなかった世界戦では、ロシアの経済状況は今よりかなりマシであっただろうし、西側諸国との関係ももっと良好であったことは確実で、欧州の二酸化炭素排出量削減ももっと進んでいたかもしれない。ロシアから安い天然ガスを買えるというのは、ヨーロッパ諸国にとってはかなり大きな意味があったからね。
だけど現実社会は、ロシアはウクライナに侵攻してしまった。その結果がグダグダである事は、多くの人の知るところである。
そしてもう一つ見落とせないのは、ロシアがやらかしたことで世界の防衛政策が一気に刷新されてしまったという点だ。NATOは復活し、欧州は軍拡に舵を切り、アジアでも日本や豪州が安全保障を強化した。
つまりロシアは「経済を壊した」だけでなく「世界の防衛体制をロシア抜きで固める」という、最悪のブーメランを投げたのである。
後から考えたら、「なんでその選択をしたんだ」ということも、歴史的にはままあることなんだよね。コレもまさにそのケースなんだけどさ。


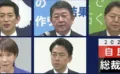

コメント
こんにちは。
大筋において、思考実験、同意であります。
・ロシアは戦うべきではなかった。機を見て、腐敗した政権を抱き込む形で子分にして、ゆるゆると併合すべきだった。
・ロシア(と中国)に対する危機感をあおる事がなければ、欧州はもっと軍縮に進み、インフラはロシア頼みになり、EUのキ○タマ握りしめていられた
・同様に、当方の島国も危機感を持たなかった(持ってもこの体たらく、というのはさておきます)
アラブとアフリカが不確定要素ではありますが、大筋こんな世界線で、ゆるゆるとダメになっていく世界だったでしょうね。国連?ダメなのがはっきりするのが速いか遅いかの違いだけで……
要は、藪蛇になった、と、後世の歴史書に書かれることを期待します。
こんにちは。
「いまさら」という話題ではあるんですが、しかし、ここへ来て色々な課題が浮き彫りになったのですから、それを前向きに捉えて準備するしかありません。